※本記事にはプロモーションが含まれています。
近年、子どもの習い事として「科学実験」や「STEAM教育(Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics)」が注目を集めています。プログラミングやロボット製作だけでなく、化学実験・電子工作・デザイン思考など幅広い分野を取り入れた教育は、単なる知識習得ではなく「自分で考え、問題を解決する力」を育むことができます。本記事では、最新のSTEAM教育系習い事のトレンドや選び方、実際の体験談、よくある質問などをまとめました。
なぜ今、科学実験・STEAM教育が注目されるのか
近年、科学実験やSTEAM教育(Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics)が急速に注目を集めています。その背景には、AIやロボット技術の発展に伴い、「これからの子どもたちが必要とする力」が大きく変化してきたことがあります。
従来の教育は、知識を暗記して正解を答える「記憶型学習」が中心でした。しかし、AIは膨大なデータを瞬時に検索し、正解を提示することが得意です。そのため、単純な暗記や計算だけでは人間が優位に立てない時代が到来しています。
一方、STEAM教育は実際に手や頭を使い、自分で仮説を立て、試行錯誤を繰り返しながら成果物を作り上げる学びです。こうした学習を通じて育まれる「創造力」「論理的思考力」「問題解決力」は、AI時代を生き抜くために不可欠なスキルといえます。
理科離れ対策としての効果
日本では長年「理科離れ」が課題とされ、理数系科目に苦手意識を持つ子どもが増えてきました。原因の一つは、学校での授業が実験よりも座学中心になってしまい、理科の面白さを体感する機会が少ないことです。
STEAM教育では、光が屈折する様子や化学反応で色が変わる瞬間など、「目で見て楽しい現象」から学びをスタートできます。この体験が理科への好奇心を刺激し、苦手意識の軽減や学力向上につながります。
自分で考えたアイデアを形にできる達成感

子どもにとって、「自分が考えたことが現実になる」経験は非常に強い成功体験になります。例えば、オリジナルのロボットをプログラミングして動かす、自由研究で発見した実験結果をまとめて発表するなど、成果物を通して自己肯定感が高まります。
達成感は次の学びへの意欲を生み、学びの好循環を作ります。これは学習意欲が低下しがちな高学年でも有効です。
将来の理系進路・海外留学にも役立つ基礎力
STEAM教育で培われる力は、将来のキャリアにも直結します。エンジニアや研究者だけでなく、デザイン、建築、データ分析など、幅広い分野で「科学的な考え方」と「創造性」の両方が求められる時代です。
さらに、海外留学や国際的なキャリアを目指す場合、理数系科目の知識に加え、英語で論理的に説明できる力が必須となります。STEAMスクールでは国際的な発表機会や英語教材を取り入れているところもあり、将来の選択肢を大きく広げることができます。
最新トレンド
① オンライン科学実験教室
コロナ禍以降、Zoomや専用アプリを使った「オンライン科学実験教室」が全国的に広がりました。事前に実験キットが自宅に届き、講師の指導を受けながらリアルタイムで実験に挑戦できます。
家庭では難しい化学反応や光学実験、生物観察なども、安全設計されたキットで安心して体験可能。親子で一緒に楽しむことで、家庭内の学びの時間も増えます。
- 送迎不要で全国どこからでも参加可能
- 親子で一緒に学べる時間が増える
- 講師がリアルタイムで質問に答えてくれる
② ロボット×科学実験の融合

従来のロボット教室はプログラミング中心でしたが、最近では「ロボットを使った科学実験」が人気を集めています。例えば、温度センサーを搭載したロボットで化学反応の温度変化を測定したり、植物の成長を自動撮影して観察するなど、工学と科学の境界を越えた学びが可能です。
このような融合型学習は、プログラミングスキルだけでなく、データ分析や科学的思考力の向上にもつながります。
③ STEAM教育×アート
近年は「理系+芸術」のハイブリッド教育も増加しています。3Dプリンターで作ったパーツを使ってアート作品を制作したり、化学反応を利用して色彩表現を行うなど、科学的知識を創作活動に活かす事例が多く見られます。
このアプローチは、論理的思考と同時に感性や独創性を伸ばし、子どもの個性を最大限に引き出します。
④ 国際的な科学コンテスト参加
一部の先進的なSTEAMスクールでは、国内外の科学コンテストやロボット競技大会への参加を目指すプログラムが用意されています。これらの大会では英語でのプレゼンテーションが求められることも多く、科学的思考力と英語力を同時に鍛えられます。
特に国際大会に参加した経験は、高校・大学の進学時にも大きなアピールポイントとなります。
STEAM教育系習い事の選び方
- 安全性:化学薬品や工具を扱う場合、安全基準の有無や講師の資格・経験を必ず確認すること。
- 対象年齢:未就学児向けか、小中高生向けかでカリキュラムや難易度が大きく異なる。
- カリキュラムの幅:科学だけでなく、プログラミング・アート・エンジニアリング要素が含まれているかをチェック。
- 継続性:単発イベントだけでなく、年間を通じて学びを深められるプログラムがあるか。
料金相場
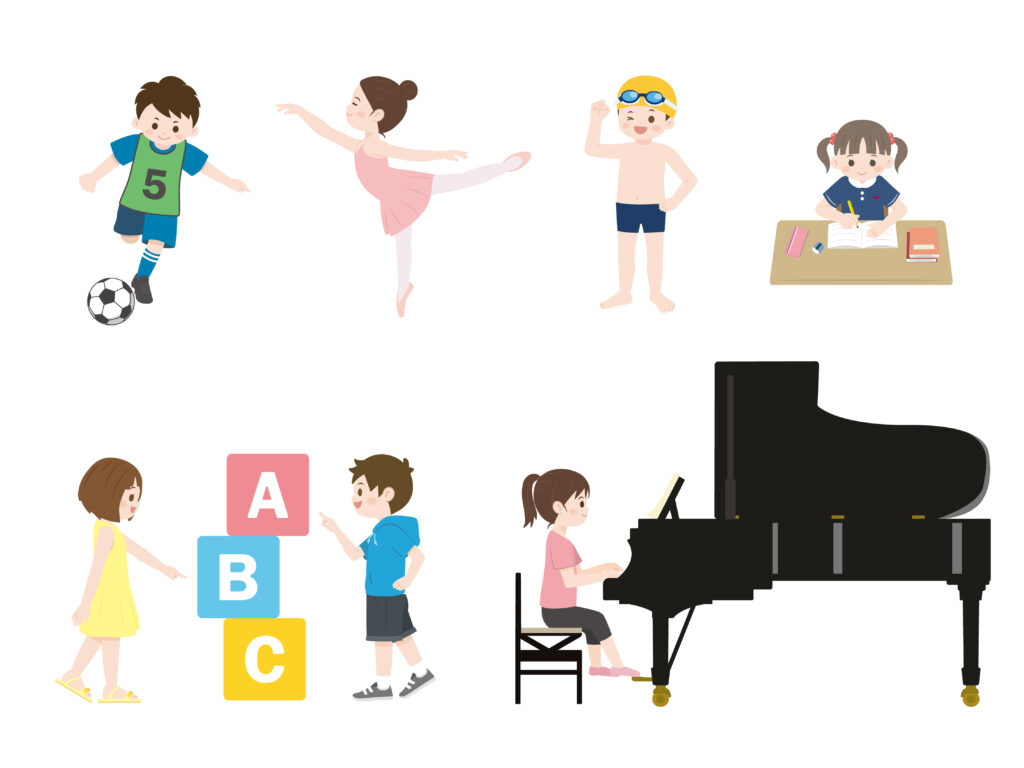
科学実験やSTEAM教育系習い事の料金は、月額5,000〜15,000円程度が一般的です。オンライン型は比較的安く、教室型やロボット教材付きコースは高めになります。
科学実験・STEAM教育系習い事の比較表
| 習い事タイプ | 対象年齢 | 特徴 | メリット | 月額費用の目安 |
|---|---|---|---|---|
| オンライン科学実験教室 | 小1〜中3 | 自宅で実験キットを使い、講師の指導を受ける | 送迎不要・全国対応・安全に学べる | 5,000〜8,000円 |
| ロボティクス&プログラミング教室 | 小3〜高3 | ロボット製作とプログラミングを融合 | 論理的思考・工学知識が身につく | 8,000〜15,000円 |
| STEAM×アート実験教室 | 年長〜中3 | 科学と芸術を組み合わせた創作活動 | 創造性・表現力・理科知識を同時に育成 | 6,000〜10,000円 |
保護者の体験談
■ オンライン科学実験を利用するママ(小4男の子)
「送迎が不要で、家で安全に実験できるのが助かります。息子は実験結果をレポートにまとめるようになり、文章力まで伸びたと感じます。」
■ ロボティクス教室に通うパパ(小6女の子)
「最初はロボットを動かすことに夢中でしたが、今ではプログラムの仕組みまで理解してきました。理数系科目の成績にも好影響が出ています。」
■ STEAMアート教室に通うママ(小2女の子)
「色と化学反応の組み合わせが面白く、作品づくりが楽しみになっているようです。家でも自主的にミニ実験をしています。」
Q&A

Q1:理系が苦手な子でも大丈夫?
A:はい、大丈夫です。科学実験やSTEAM教育系のカリキュラムは、公式や難しい理論をいきなり学ぶのではなく、「色が変わる不思議な水」「ペットボトルロケットを飛ばす」「動くロボットを作る」など、好奇心をくすぐるアクティビティから始まります。
遊び感覚で進められるため、理科や数学への苦手意識が自然と薄れていくケースが多いです。例えば、理科テストで苦手だった子が、実験で培った「観察する力」を活かし、授業内容の理解が深まった例もあります。
むしろ、苦手な子こそ「実際に見て触れて学ぶ」環境が効果的で、理系科目を好きになるきっかけになることが多いです。
Q2:家庭でのフォローは必要?
A:必須ではありませんが、家庭でのちょっとしたフォローが学びの定着を大きく助けます。例えば、子供が授業で作ったロボットや化学実験の成果物を飾ったり、テーマに関連する本や動画を一緒に見たりすると、興味が長く続きます。
また、次の授業までの間に「これってどういう仕組みなんだろう?」と一緒に調べると、調べ学習の習慣も自然に身につきます。
ただし、過度に口を出す必要はなく、「面白かった?」と感想を聞く程度でも十分。子供が主体的に話し出す環境を作ることが大切です。
Q3:費用を抑える方法は?
A:費用を抑えるには、いくつかの方法があります。
1つは、オンライン型の科学教室やプログラミング講座を利用すること。通学型よりも料金が安いケースが多く、移動時間もゼロで効率的です。
2つ目は、自治体や科学館が主催する「週末科学教室」や「子供向けワークショップ」に参加する方法。低価格、もしくは無料で参加できることもあります。
3つ目は、民間スクールが行う期間限定の体験キャンペーンや入会金無料キャンペーンを狙うこと。
さらに、家でできる低コスト実験キットを活用すれば、習い事との併用で費用を抑えつつ学びの幅を広げられます。
まとめ
科学実験・STEAM教育系の習い事は、AI時代を生き抜くための必須スキルを自然に身につけられる学び方です。オンラインから教室型、国際的なコンテスト参加まで選択肢は幅広く、子どもの興味や性格に合わせて選ぶことで、学びがより充実します。2025年の今こそ、未来につながる教育投資を始めてみてはいかがでしょうか。

